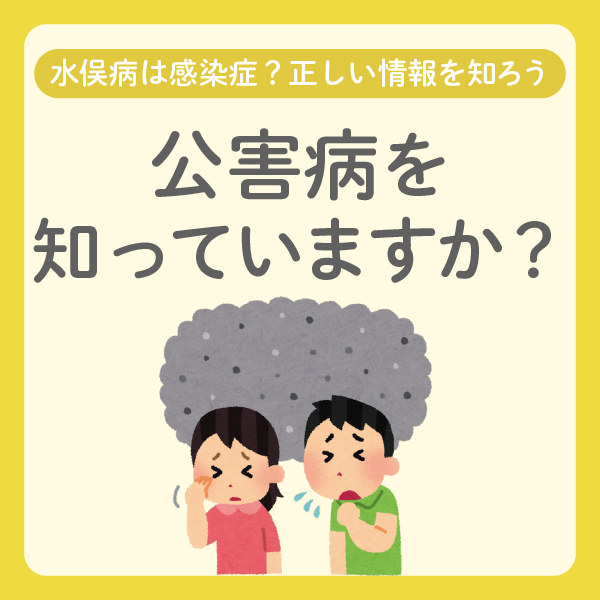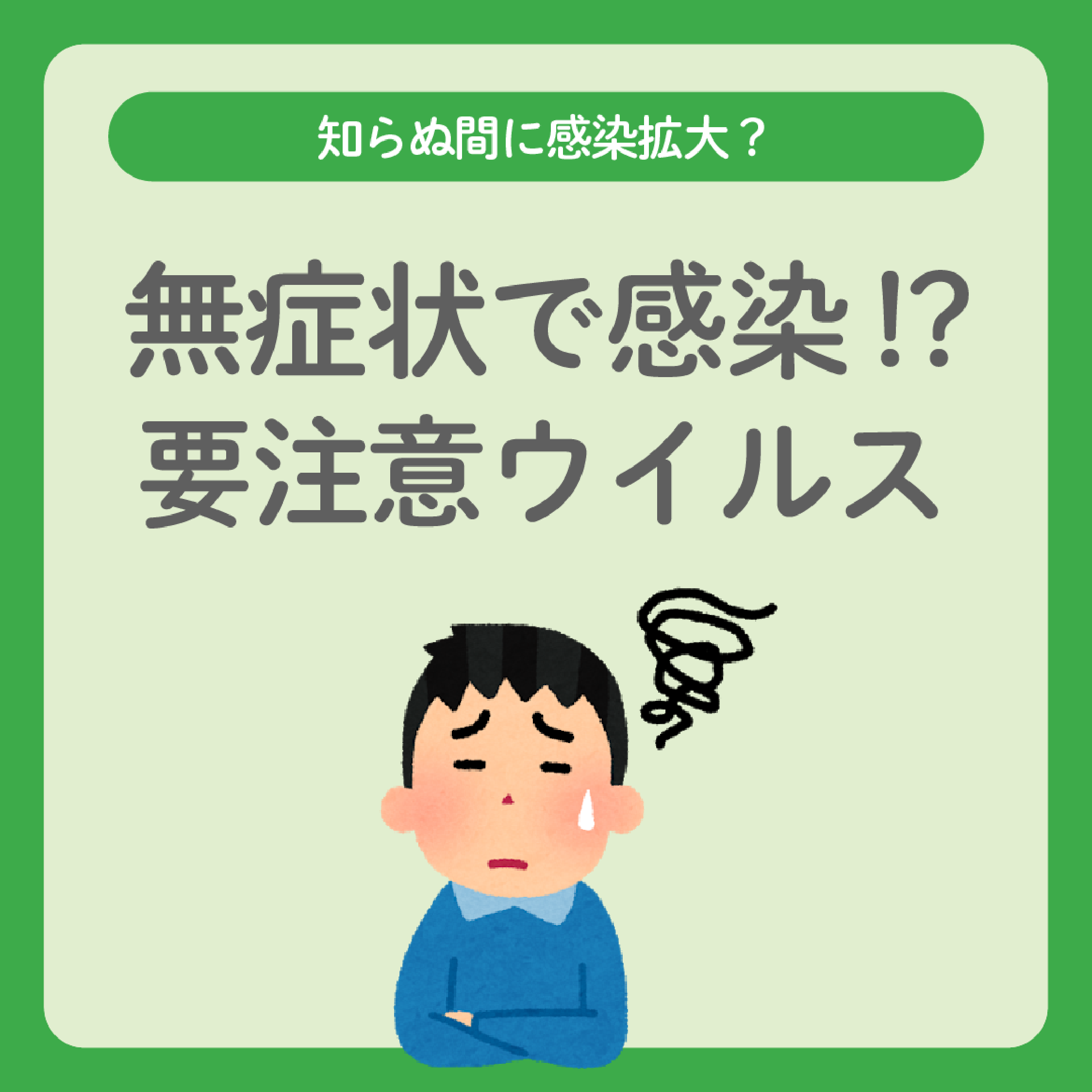【文豪と感染症】
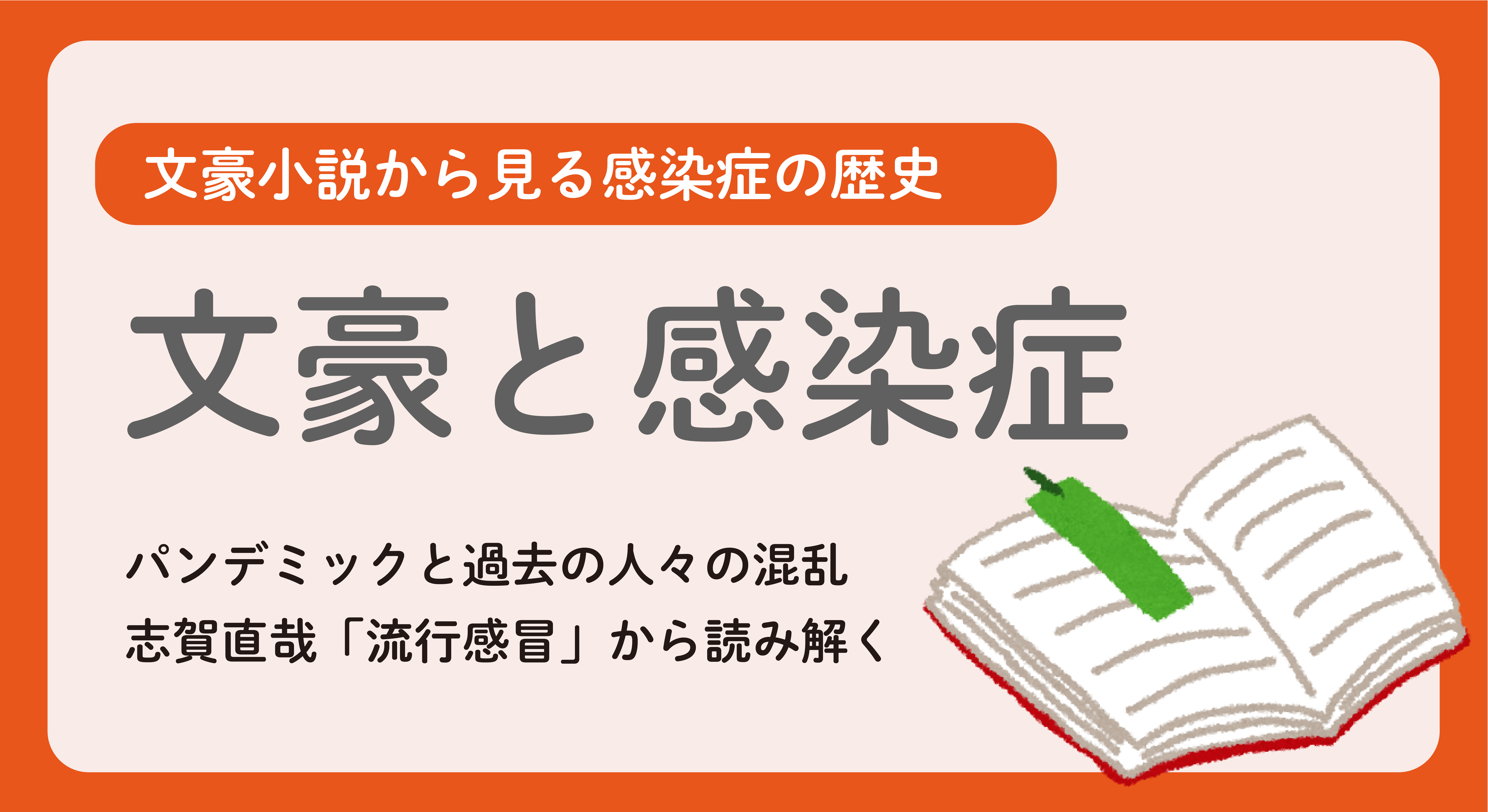
感染症にかかって亡くなった文豪たちと感染症への偏見
新型コロナウイルスによるパンデミックが始まった頃、私たち現代人は混乱の渦に飲まれました。
同じように、過去の日本人たちも感染症を恐れ、混乱した時代が幾度となくありました。
例えば「結核」は、特効薬が作られる戦後まで不治の病とされていました。また、1918年から大流行した「スペイン風邪」(インフルエンザ)なども同様で、これらの感染症は治療法が確立していなかった当時、死亡率が非常に髙いものとして人々に恐れられてました。
こうしたパンデミックによる世界の混乱は、文学作品にも多く描かれています。
志賀直哉の小説「流行感冒」では、スペインか風邪が大流行した1918−1921年ごろを舞台として描かれています。
主人公が多く集まる場所には行かないように徹底しており、当時の人々も、現代のコロナ禍と同じように生活をしていたようです。
ところが、家の女中が町で行われた芝居興行にこっそり出かけたことを知り、それに腹を立て追い出そうとしますが、妻に止められ断念します。
その後、家に出入りの職人から家族全員が感染し、高熱になって苦しみますが、この女中はスペイン風邪にかからず、みんなの世話をしたおかげで家族は助かります。そこで、主人公は女中への態度を反省します。
この小説は、志賀直哉自身が「事実をありのままに書いた」と言っている私小説です。
つまり、文豪でも、パンデミックの混乱によるストレスや不安感に襲われ、他人に攻撃的になったり、尊重することを忘れてしまうということです。
現代のパンデミックでも「自衛警察」という言葉が生まれたり、初期には感染者を攻撃する人も多くいました。
志賀直哉は1883年2月20日生まれ、100年以上も前の、過去の人々が感染症に何を思ったか、本を読んで思索を深めてみるのもいいかもしれません。