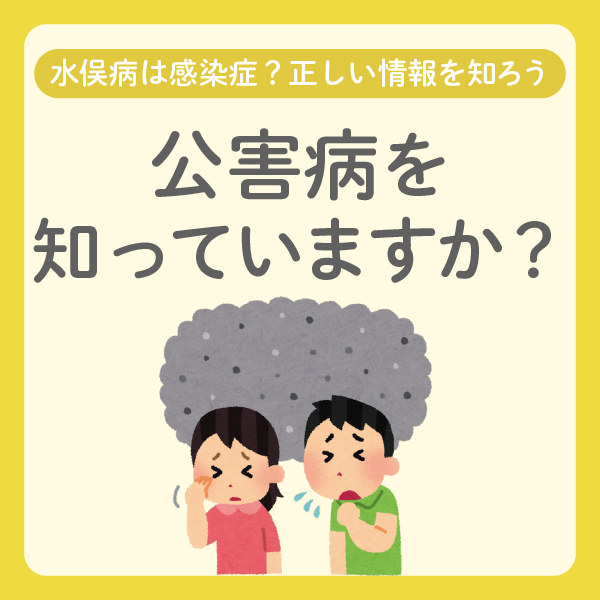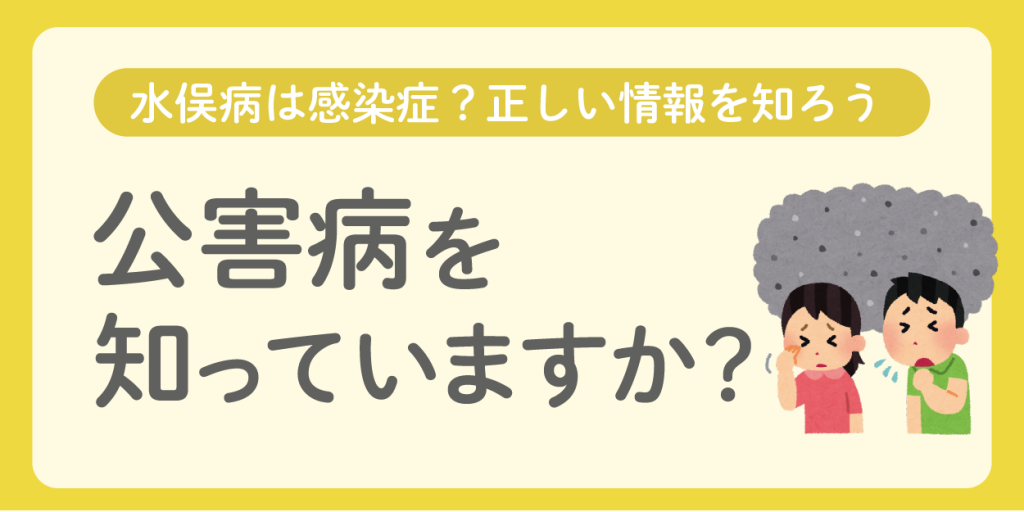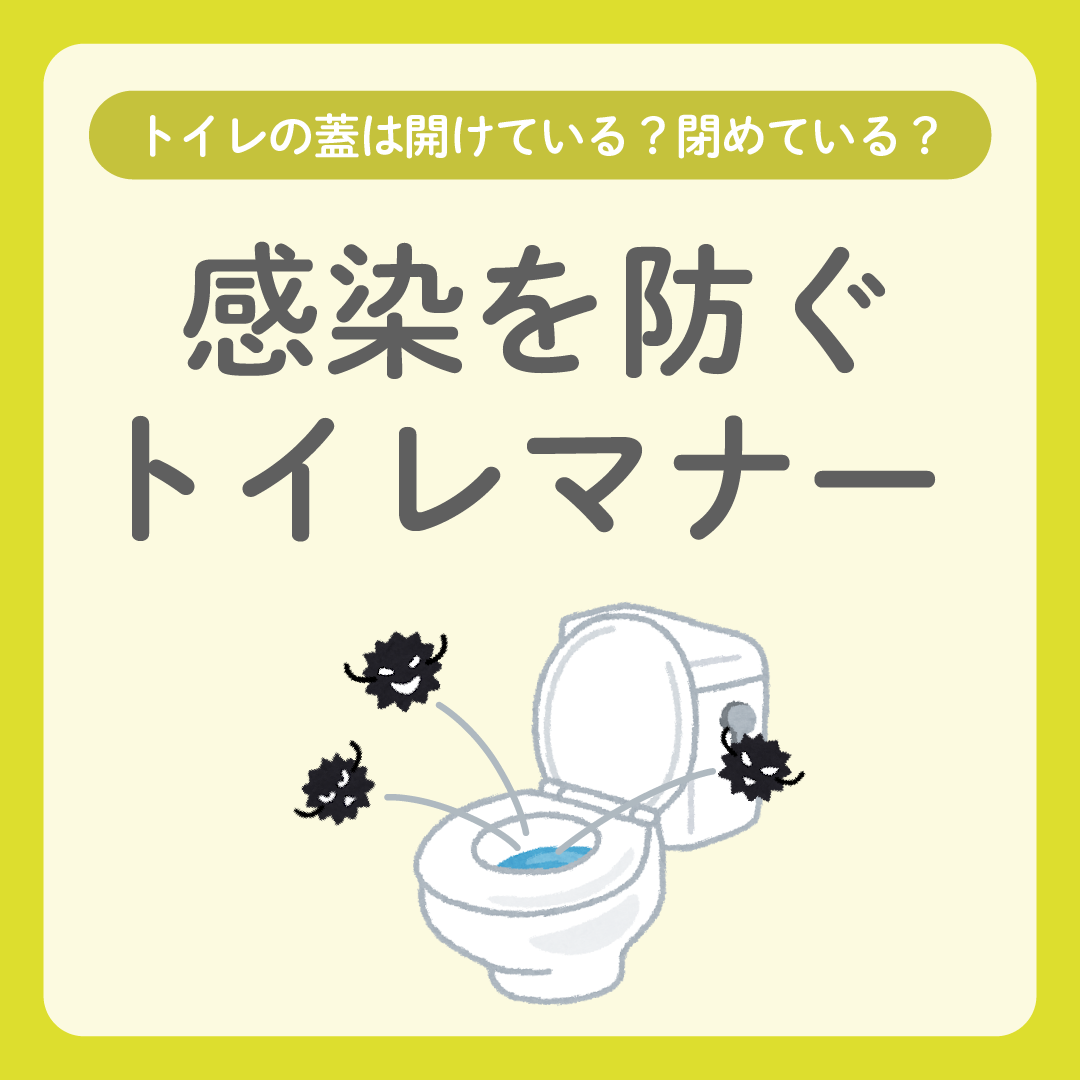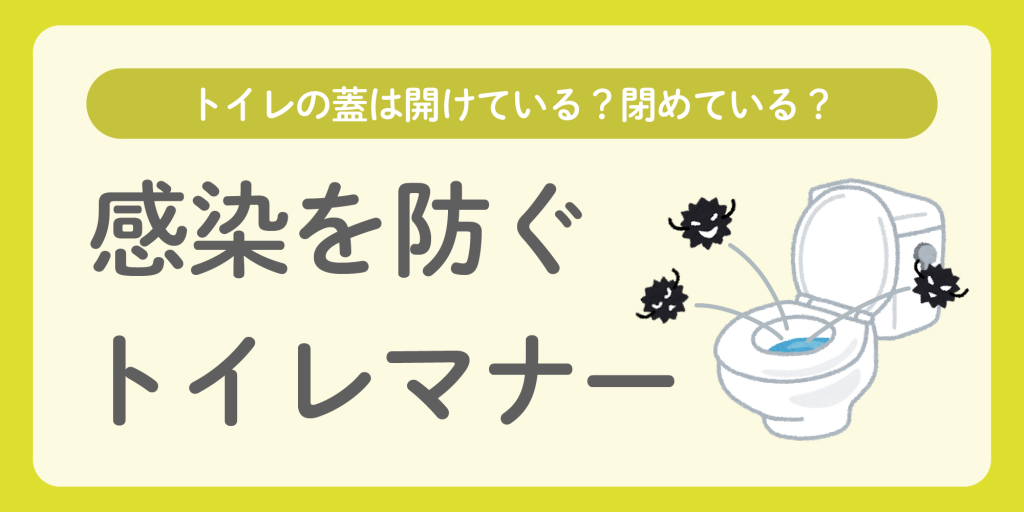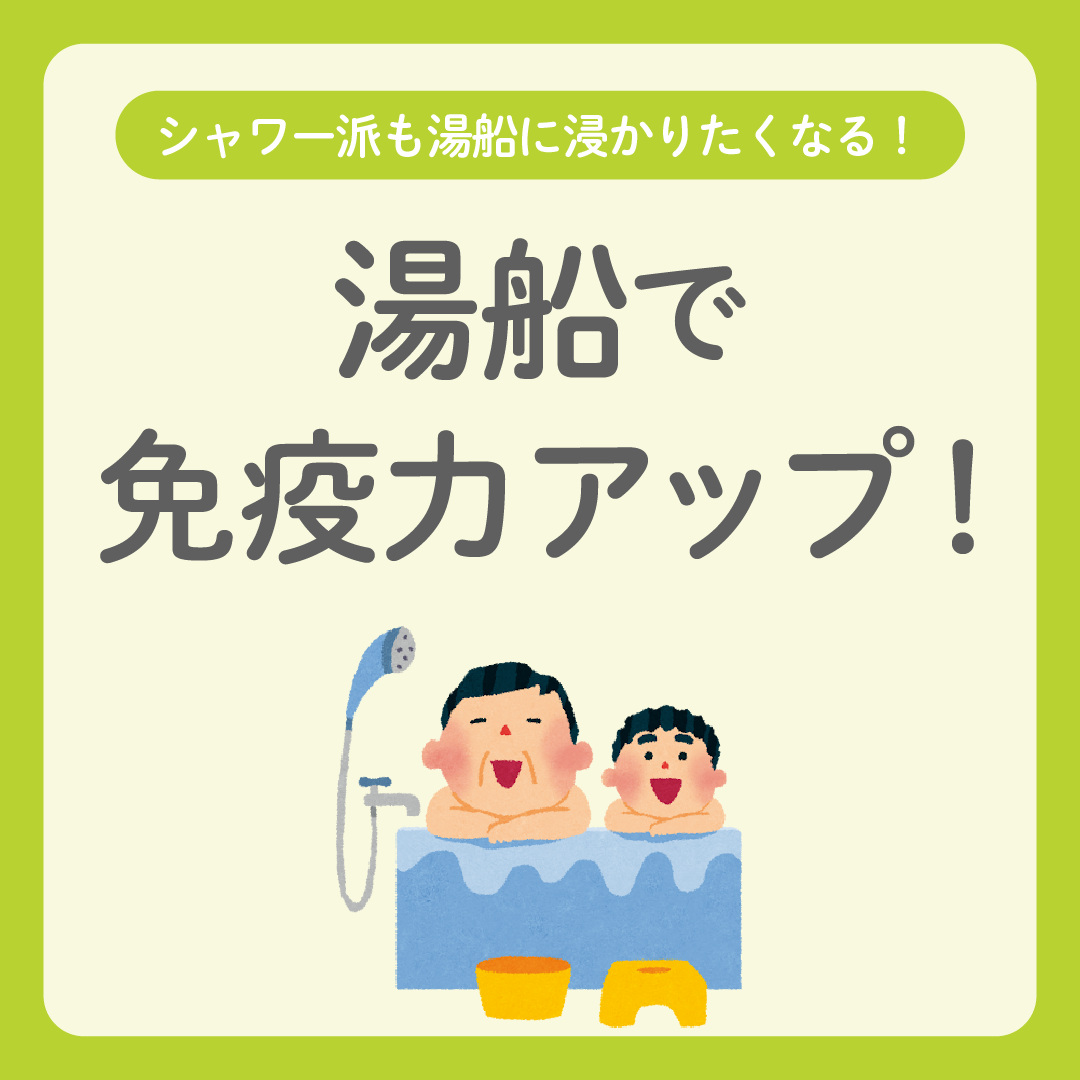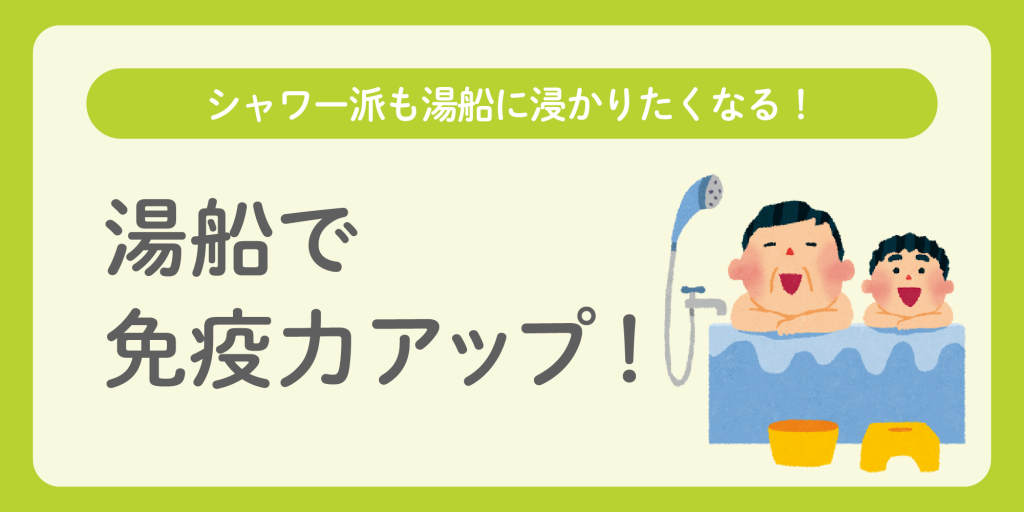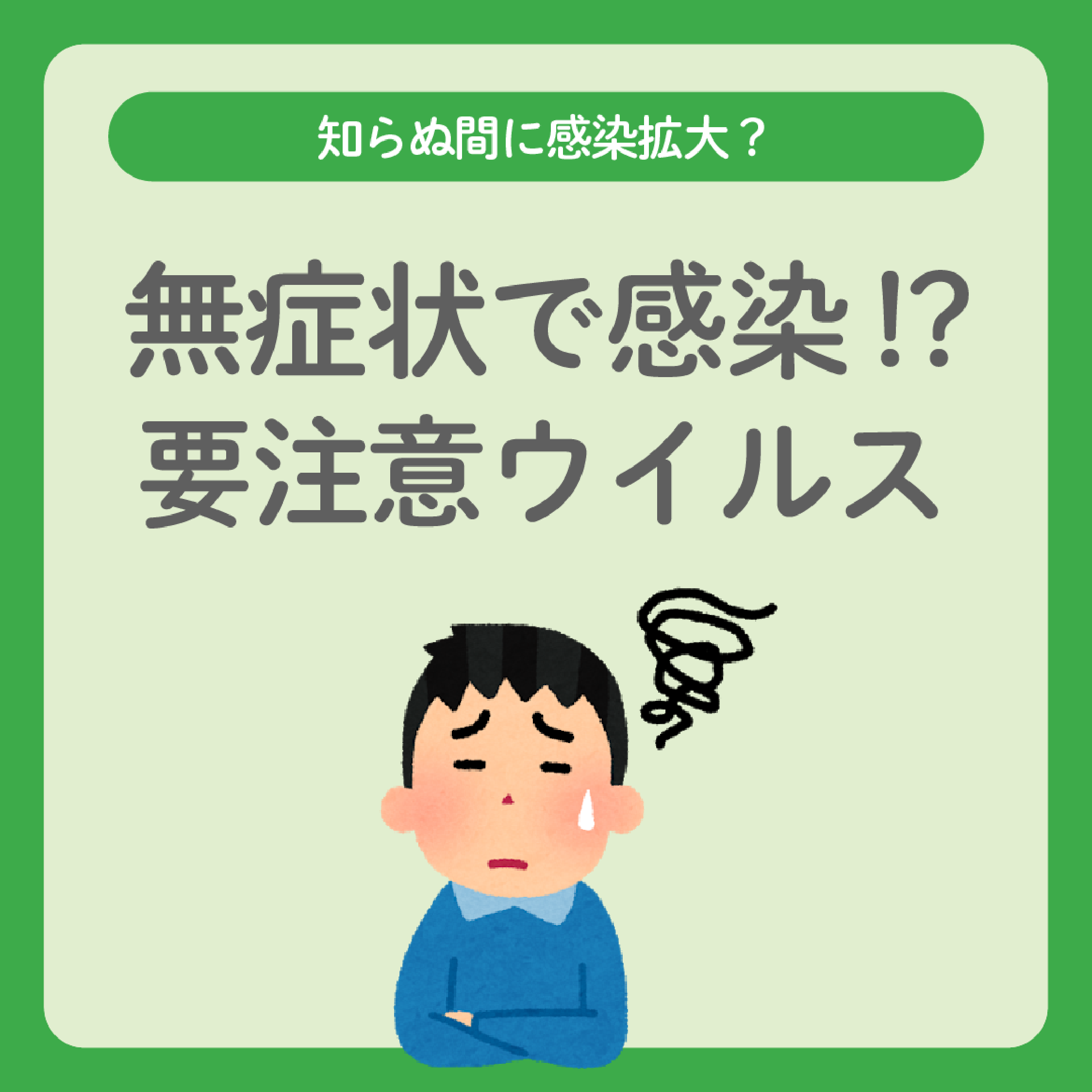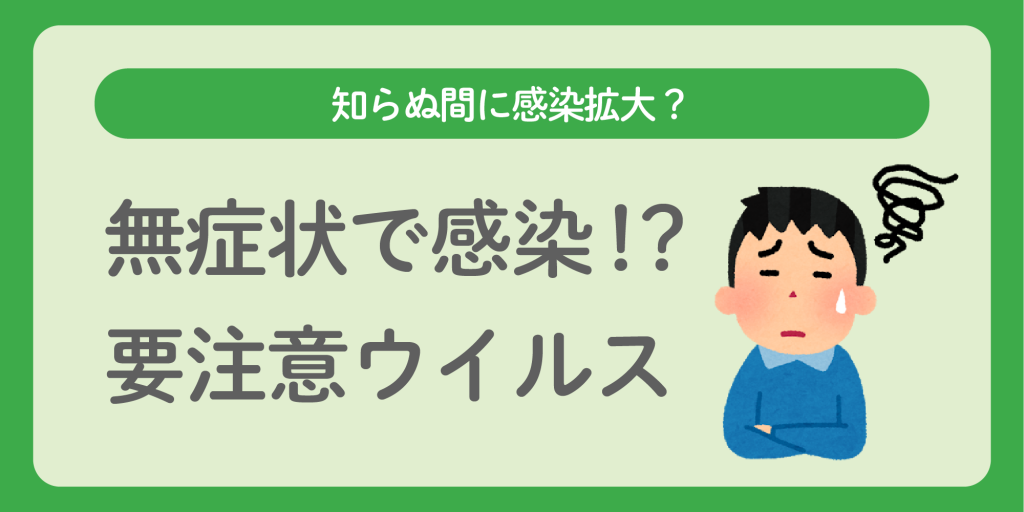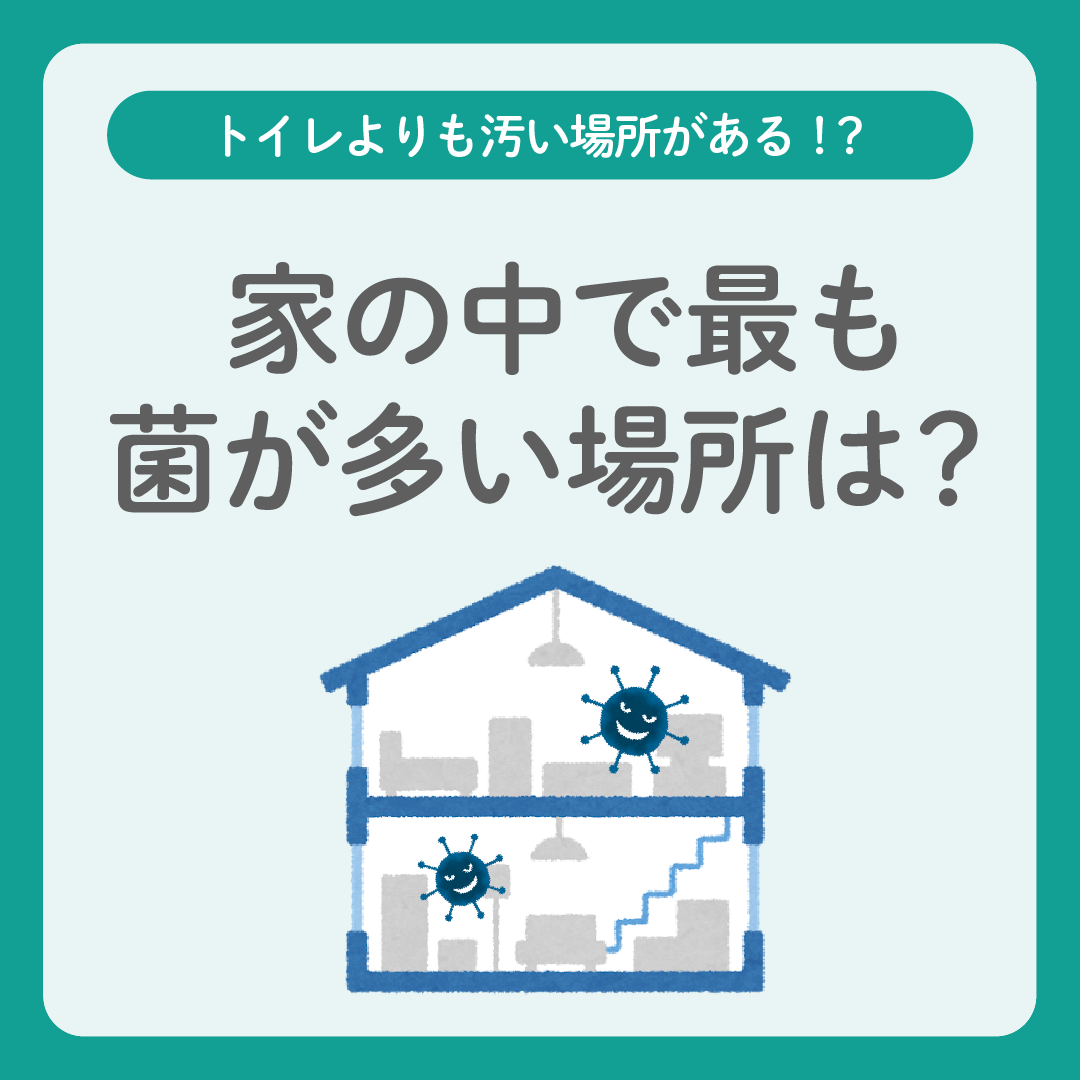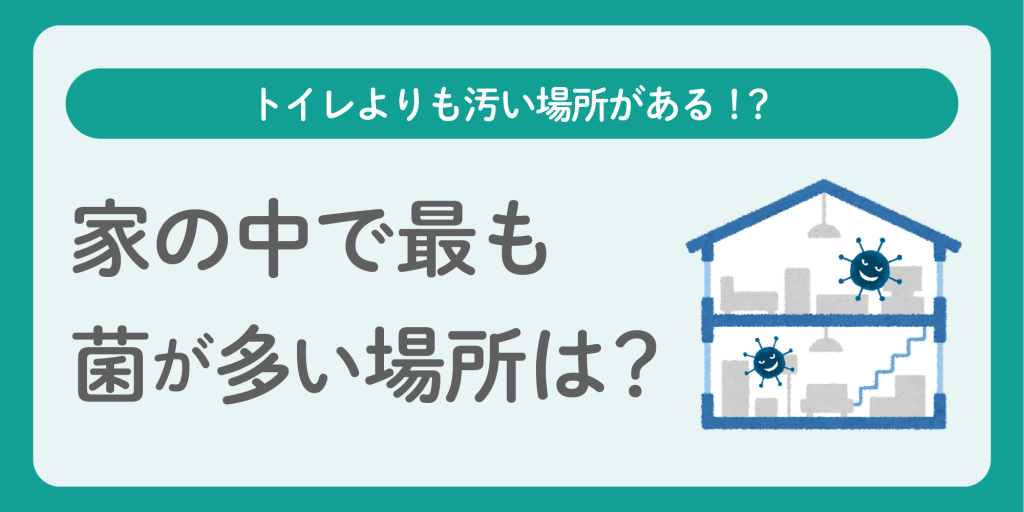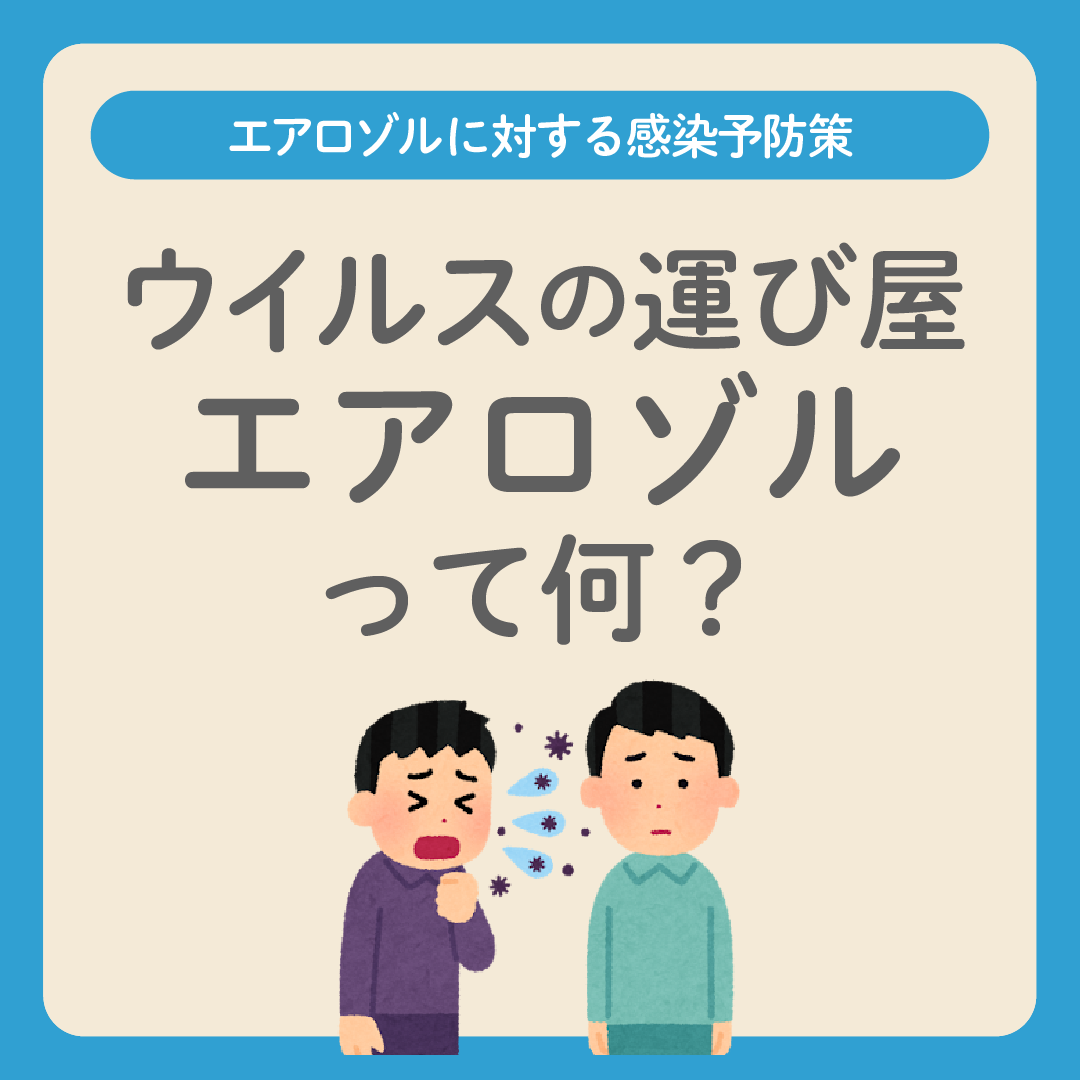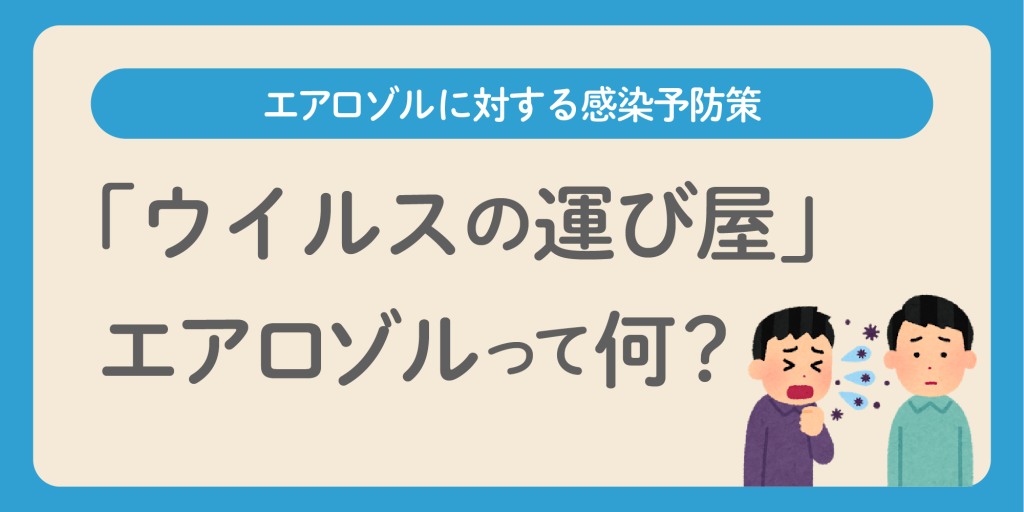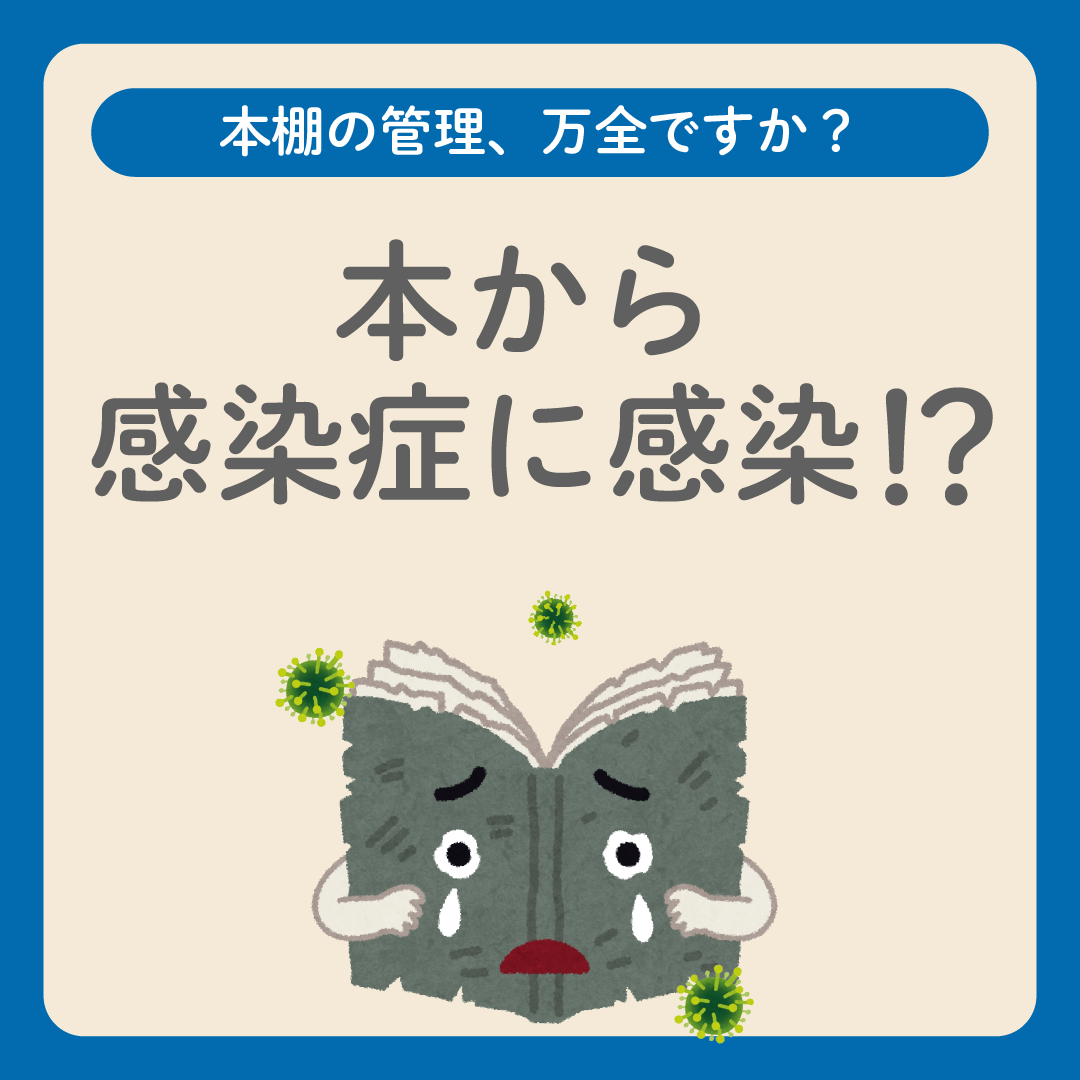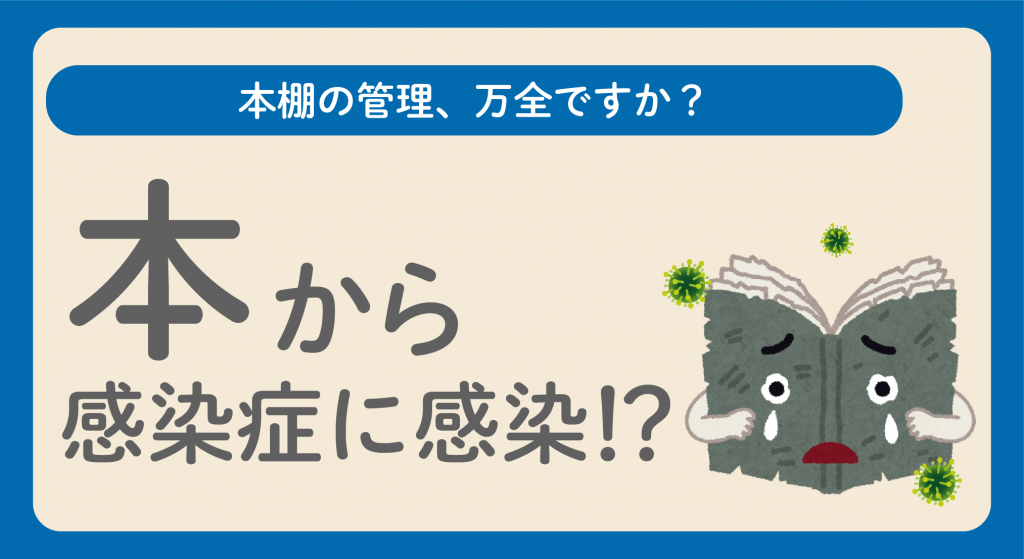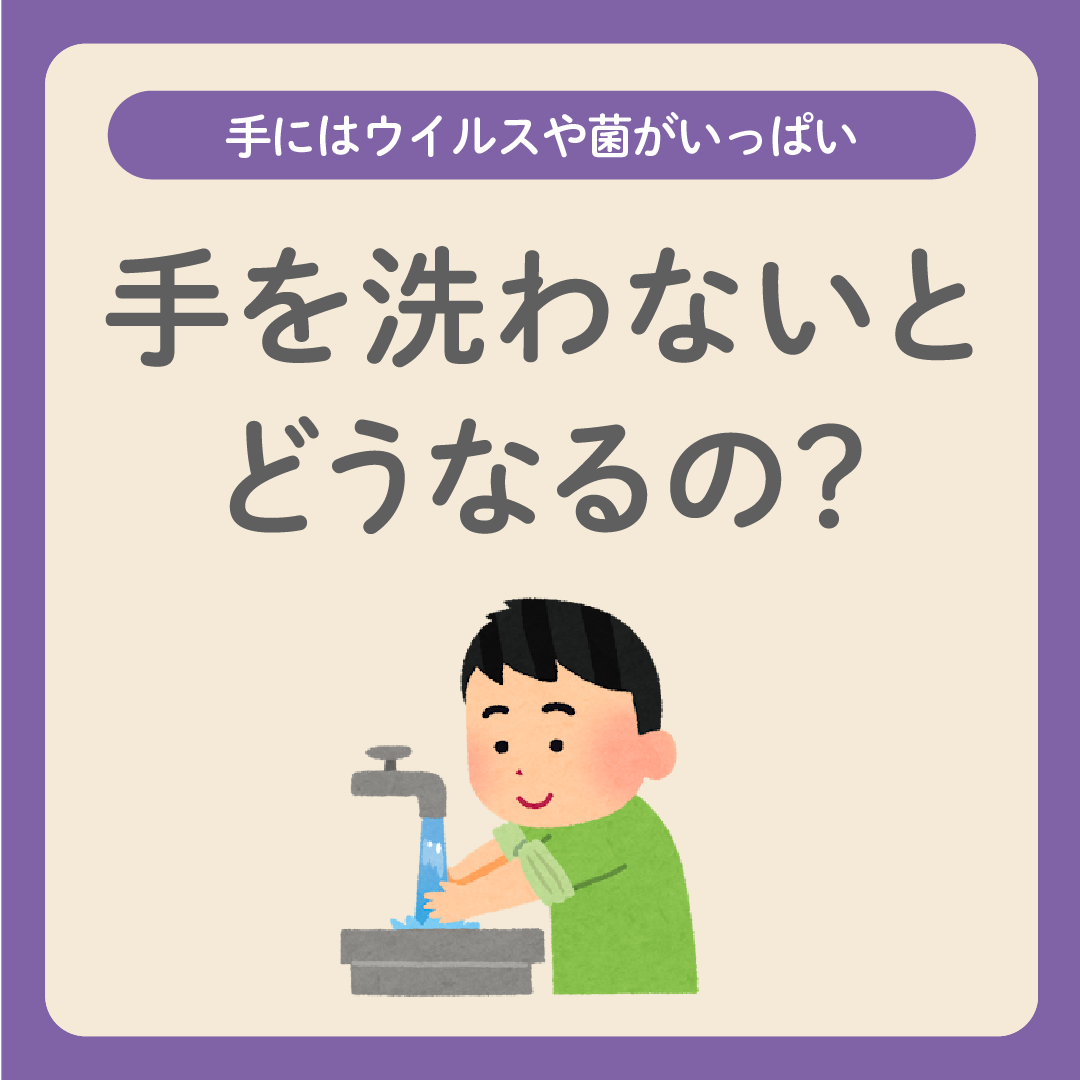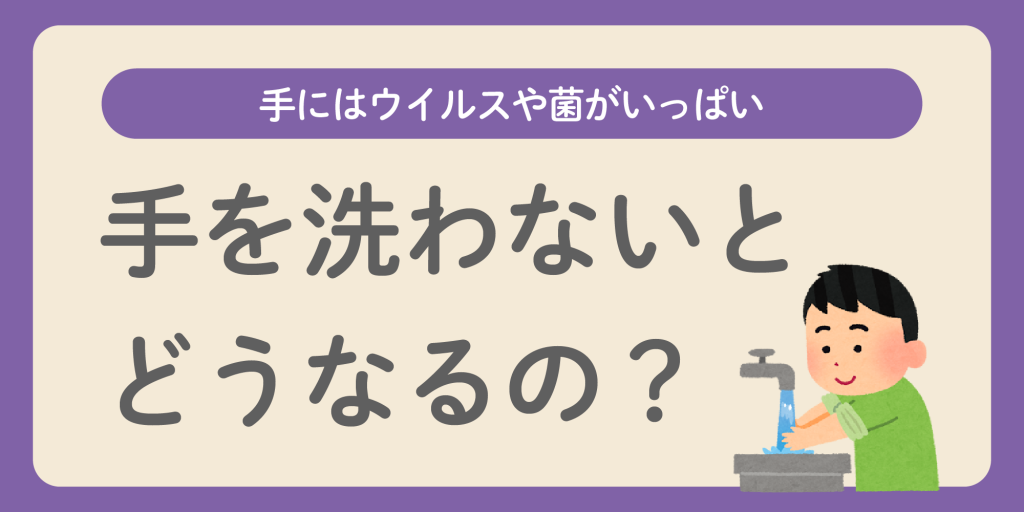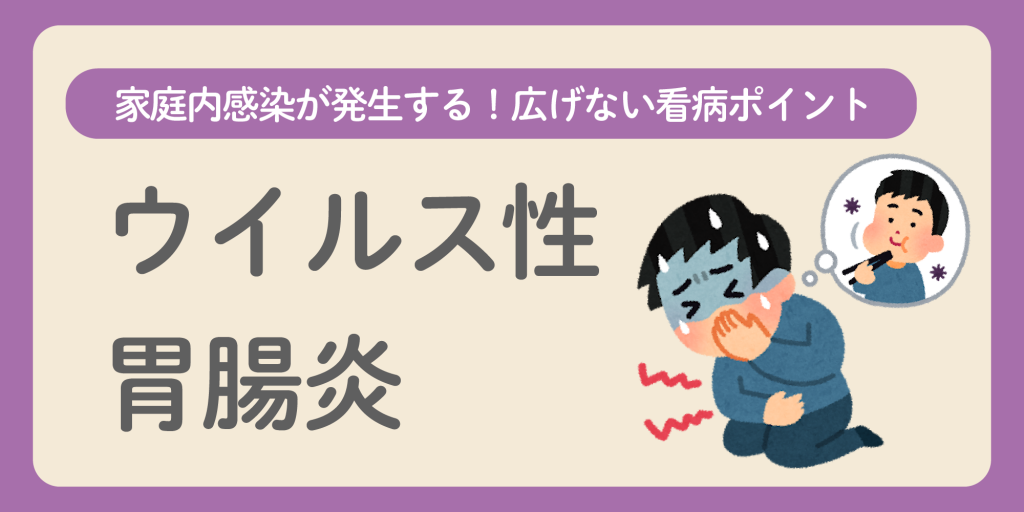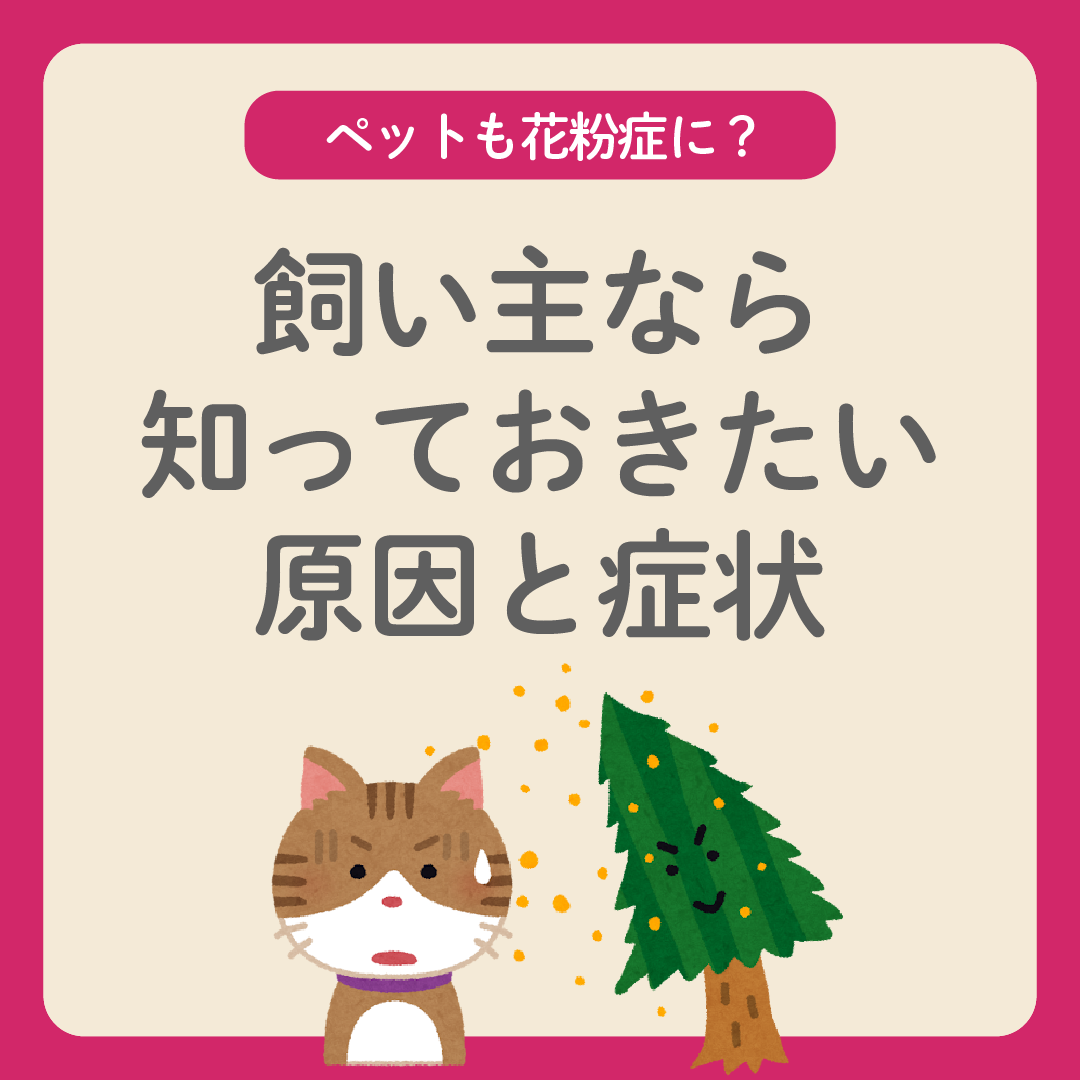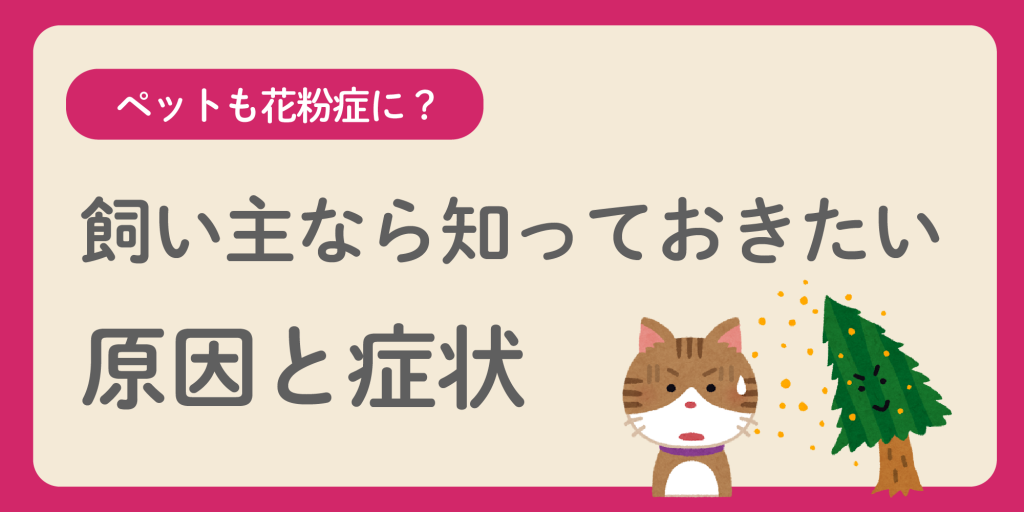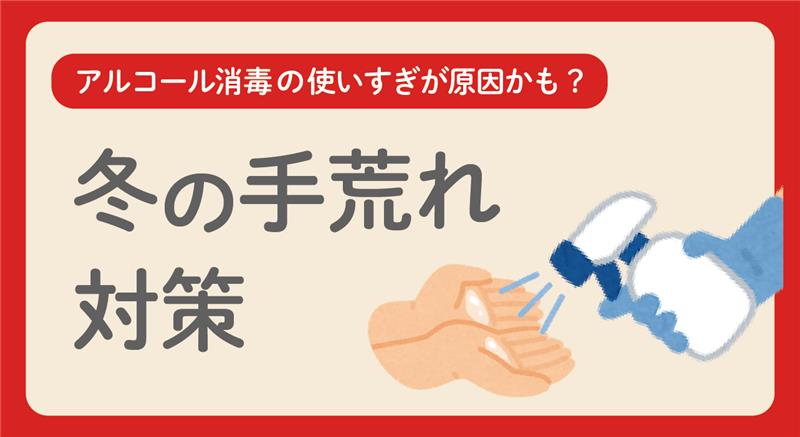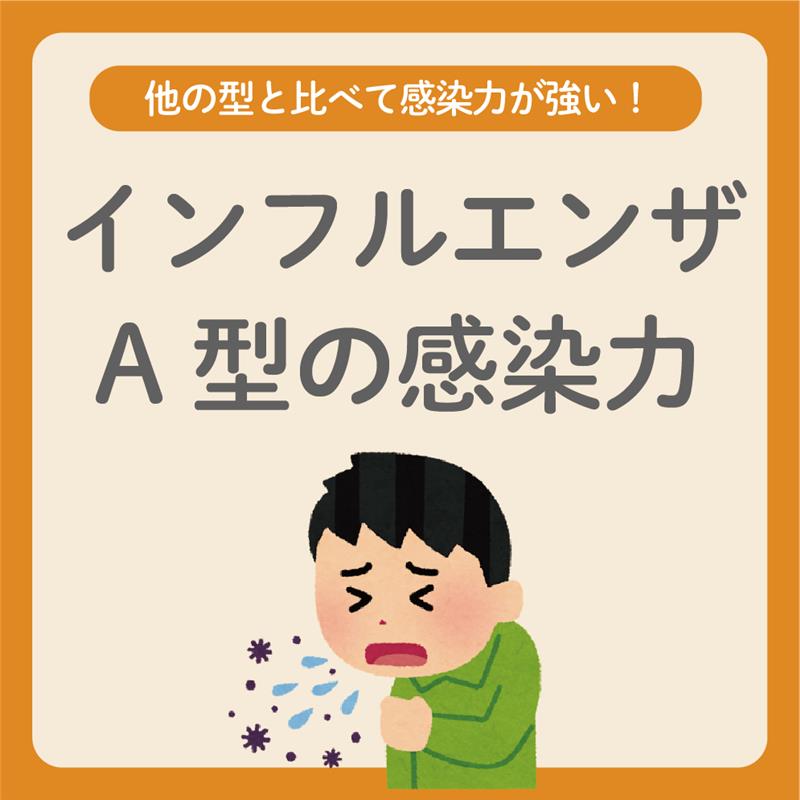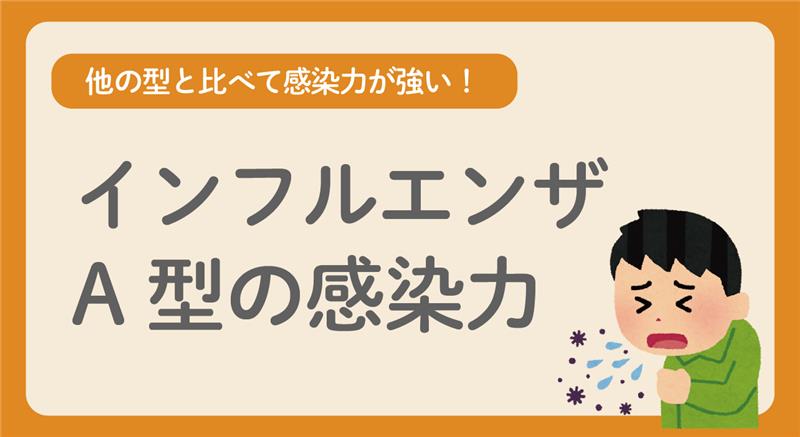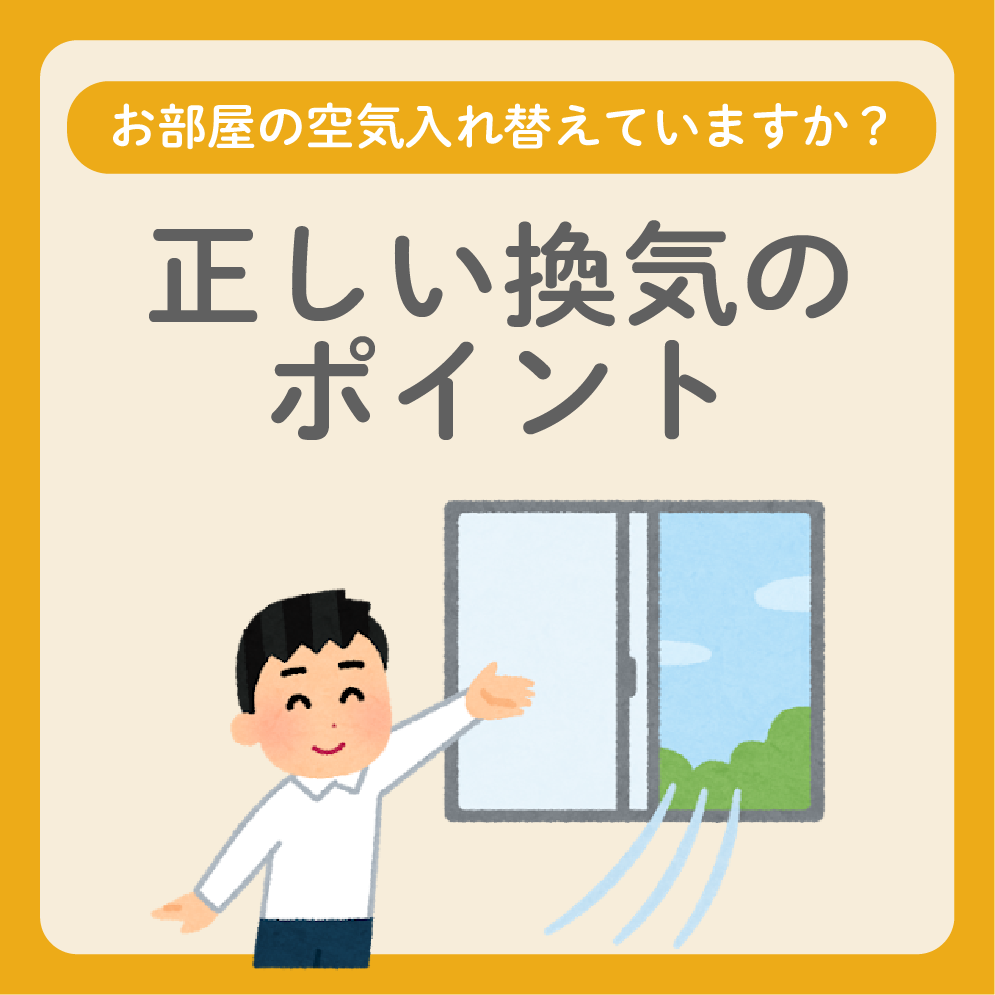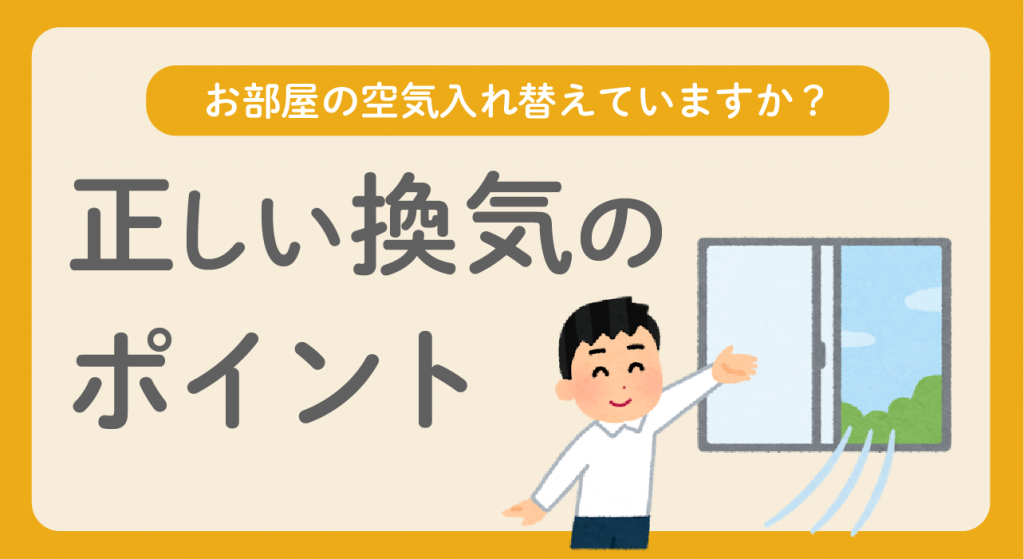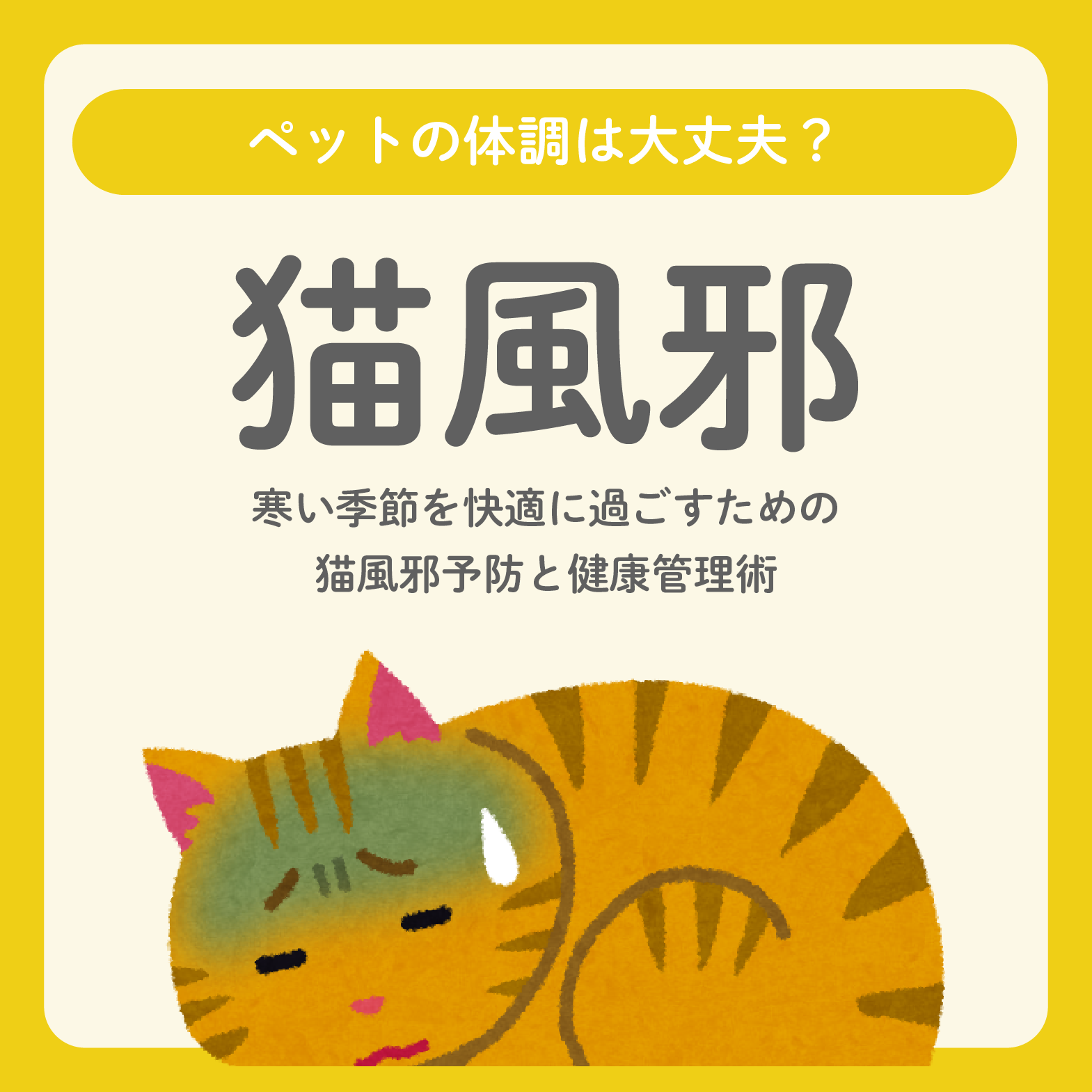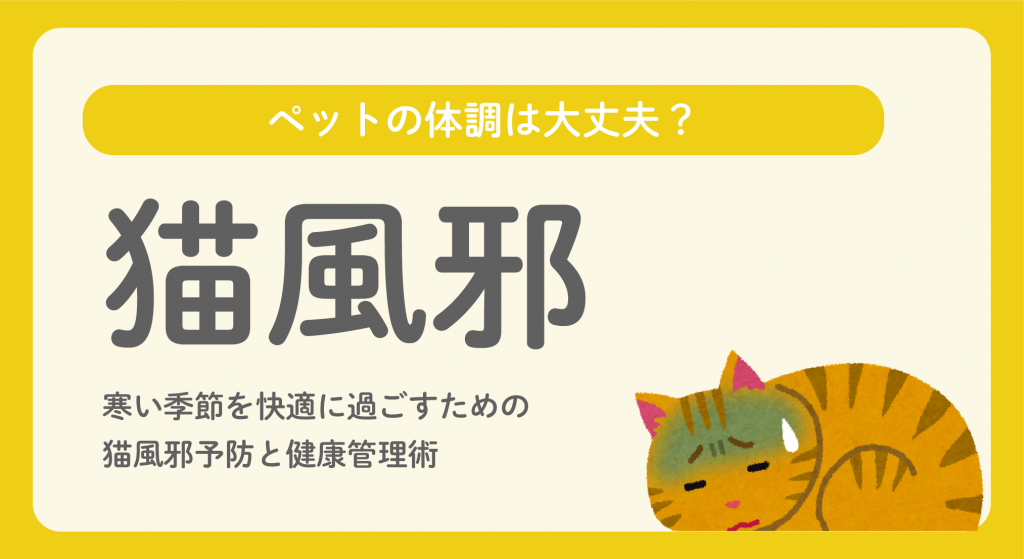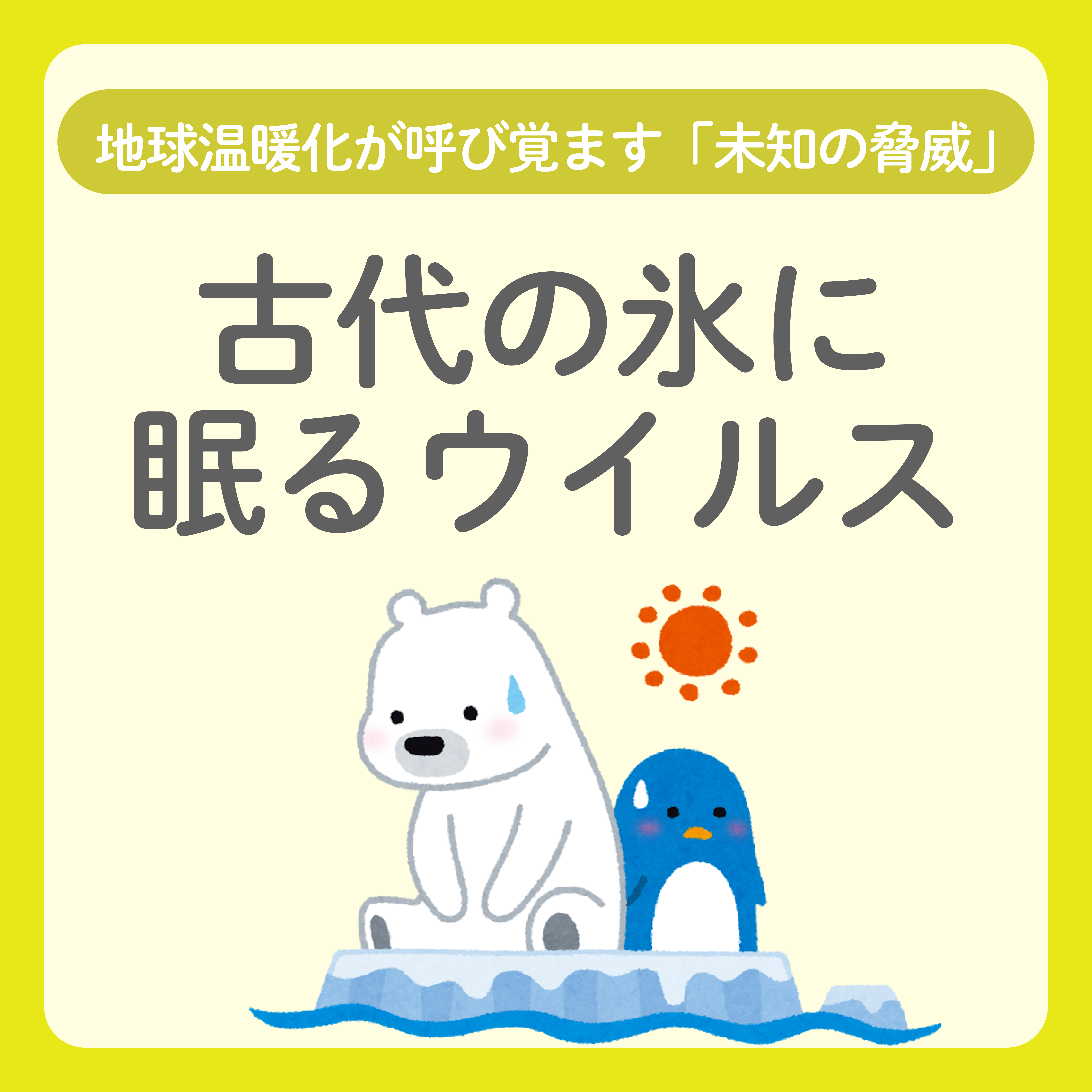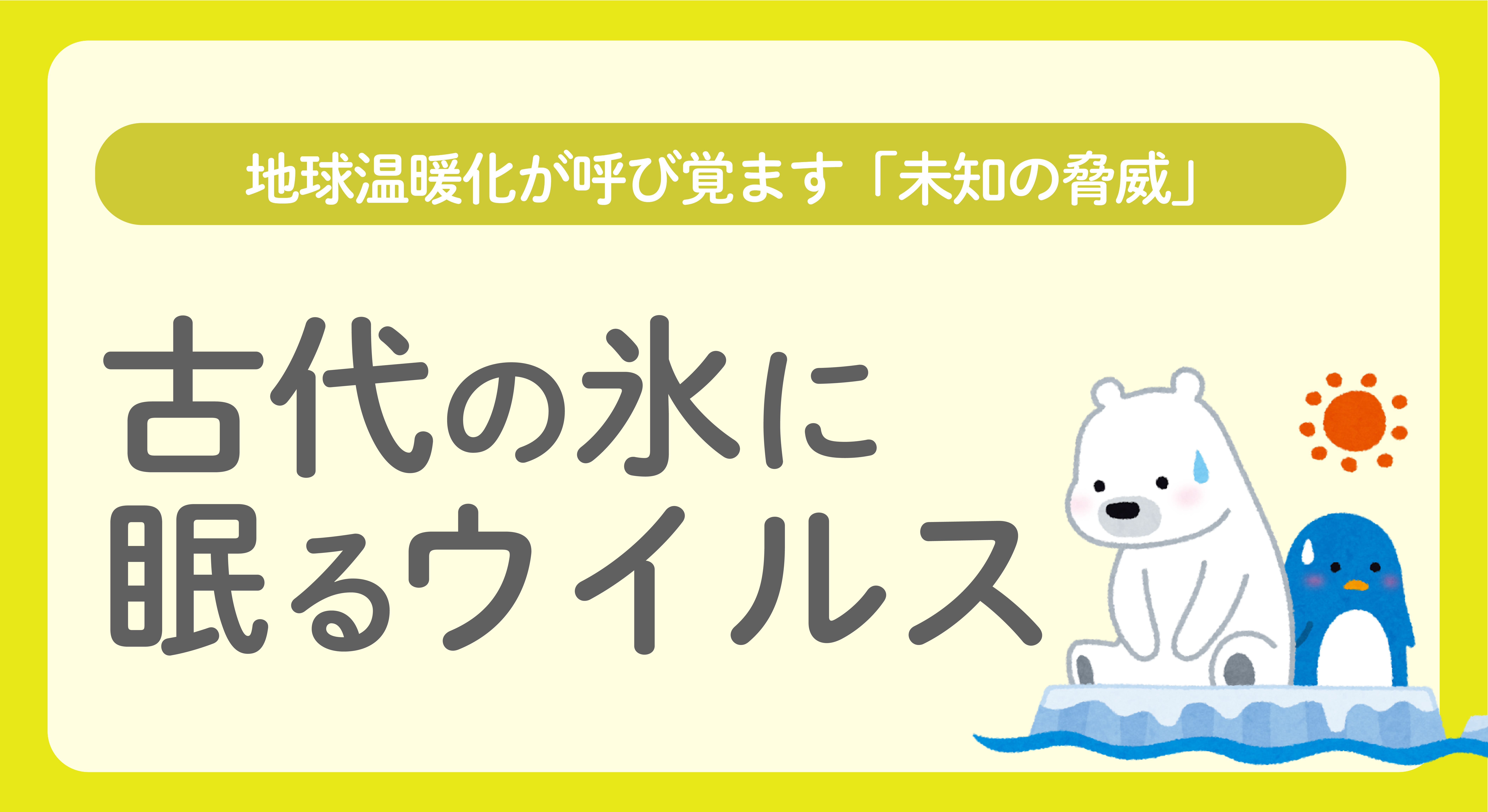【寄生虫感染症で最多報告数!アメーバ赤痢とはどんな病気?】
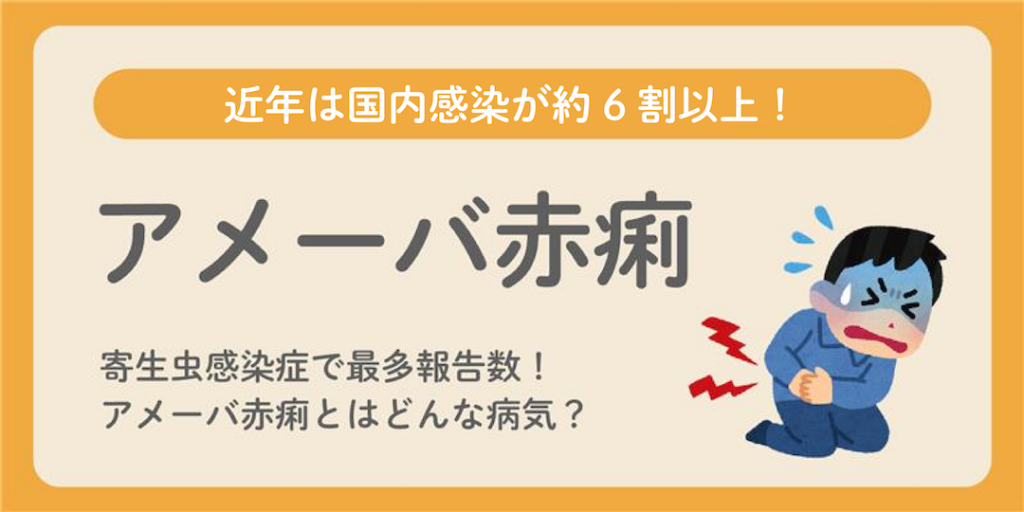
こんにちは、デンネツ広報担当です。
皆さんは「アメーバ赤痢(正式名称:赤痢アメーバ症)」という感染症をご存じでしょうか?
日本ではあまり知られていないものの、実は寄生虫感染症の中で最も多く報告されている疾患です。今回は、この意外と身近な「アメーバ赤痢」について、病気の概要や症状、感染経路などをわかりやすくご紹介します。
〈赤痢アメーバ症とは?〉
赤痢アメーバ(Entamoeba histolytica)という微小な寄生虫が、大腸に感染して炎症を引き起こす病気です。
この寄生虫は、感染者の便とともに排出された後も、特に**「シスト型」と呼ばれる状態**では環境中で長期間生存し、感染力を保ち続けます。
そのため、無症状の保菌者からも感染が広がるリスクがあります。日本ではあまり馴染みがないように思えるかもしれませんが、実際には年間数百件以上の感染報告があり、誰にでも感染の可能性があります。
〈どんな症状が出るのか?〉
・腹痛
・下痢や血便
・発熱、倦怠感、体重の減少
こうした症状が長引くと、腸に出血が起こったり、重症化する恐れもあります。「いつもの下痢かな」と油断せず、気になる症状が続く場合は早めに医療機関を受診しましょう。
〈感染経路は?〉
主な感染経路は「経口感染」と「糞口感染」です。特に赤痢アメーバの「シスト型」は感染者の便から環境中に排出されるため、汚れた手で食事をしたり、十分に洗浄されていない野菜を生で食べたり、汚染された水や氷を口にすることで体内に入り感染することがあります。
赤痢アメーバ症は、薬で治療可能な感染症です。
体調に異変を感じた場合は早めに医療機関を受診し、周囲に感染を広げないよう対策をとることが大切です。