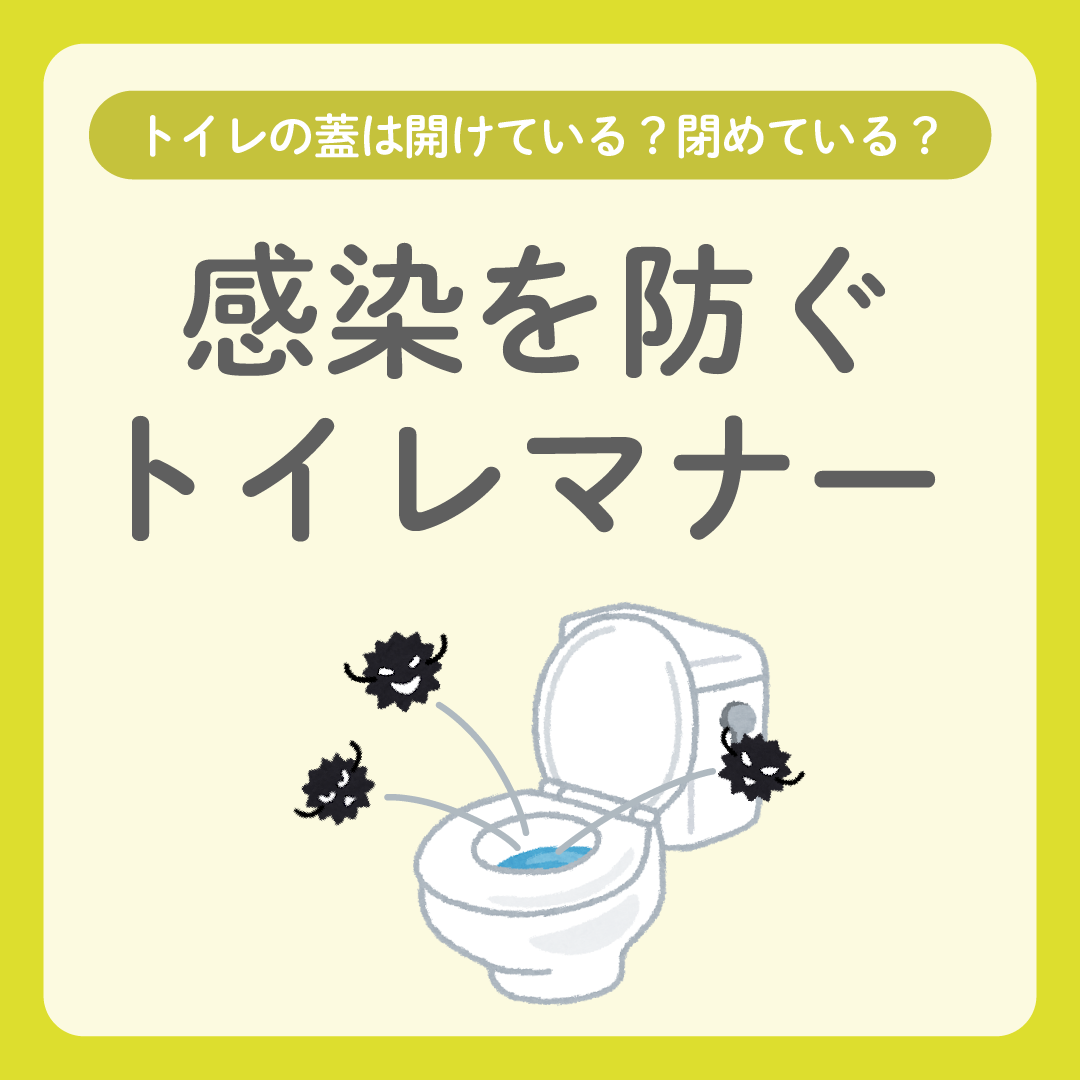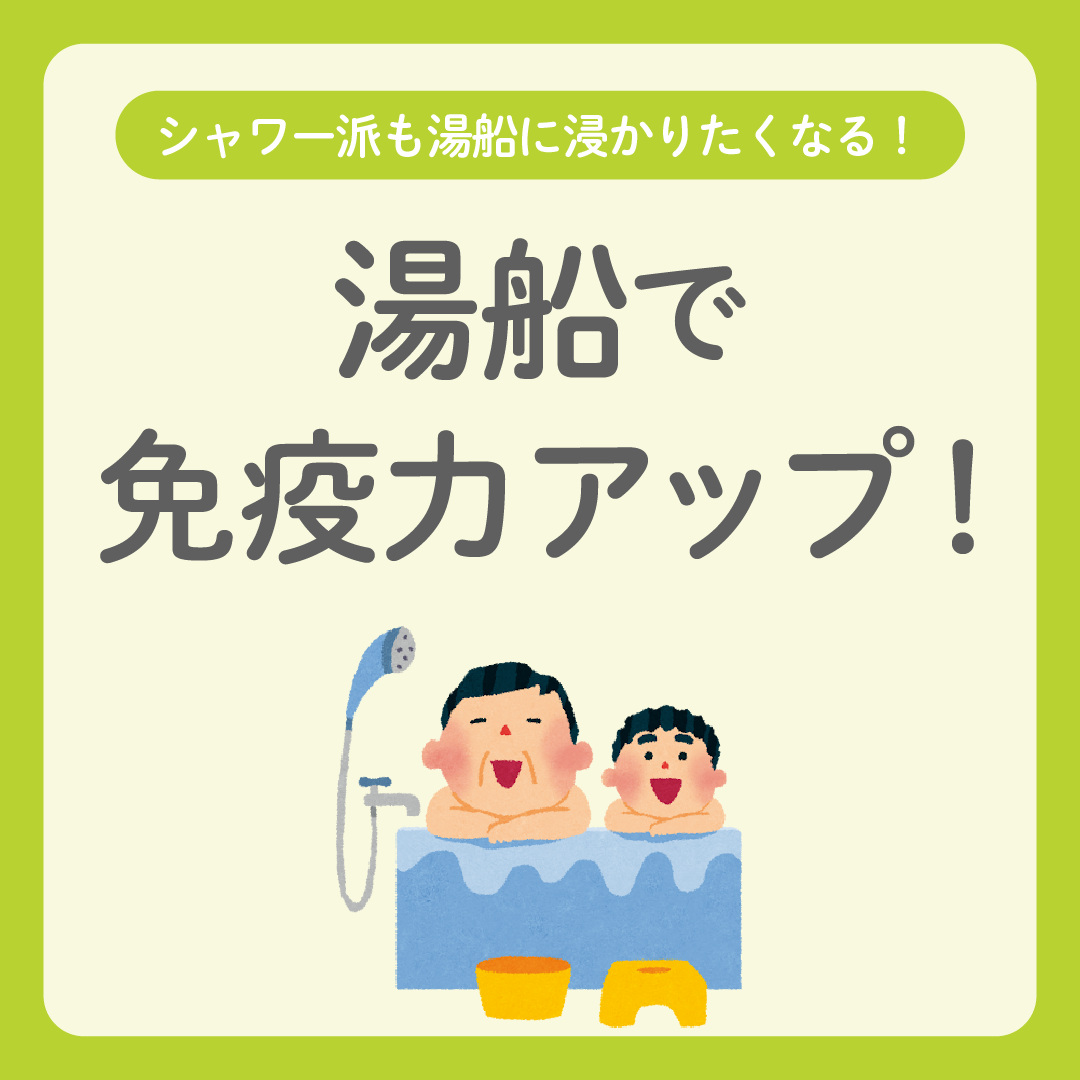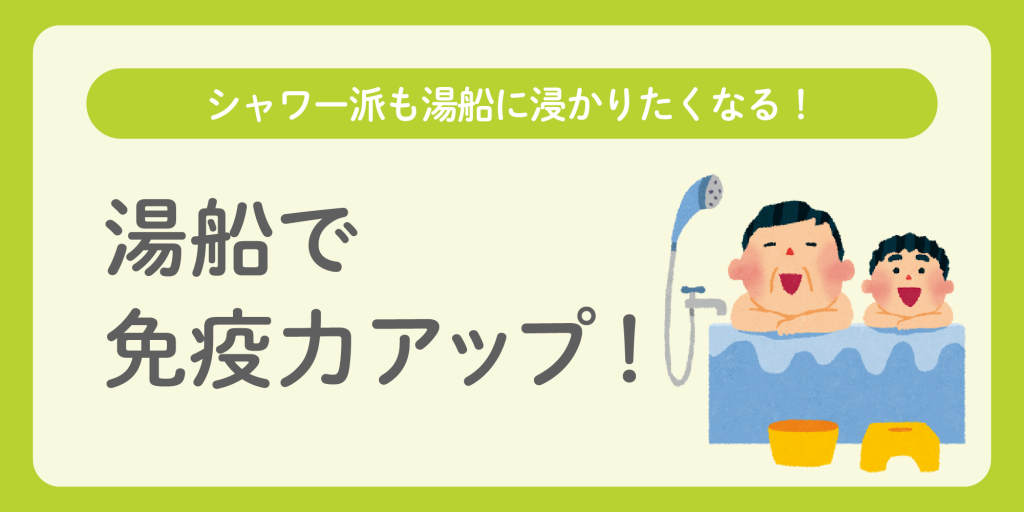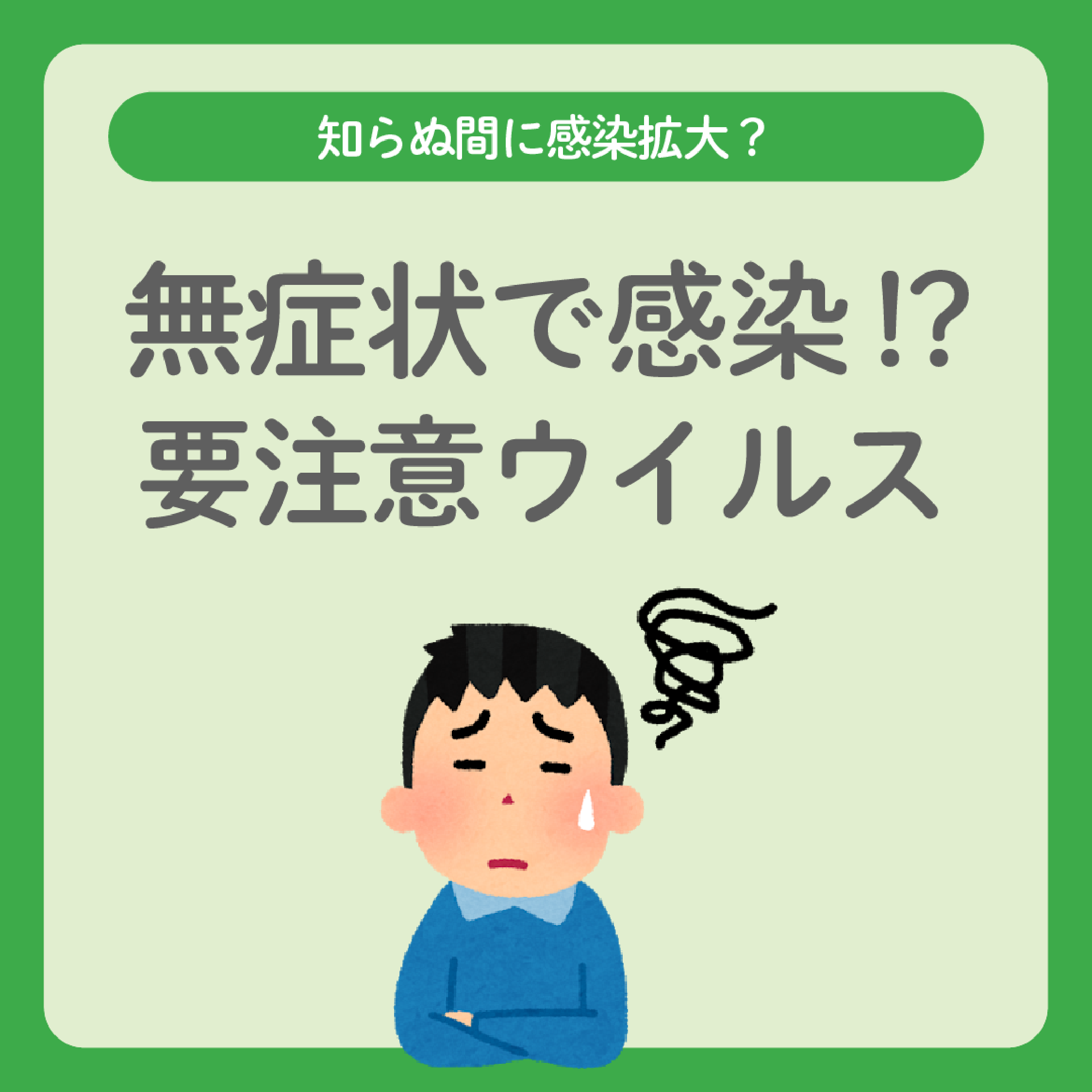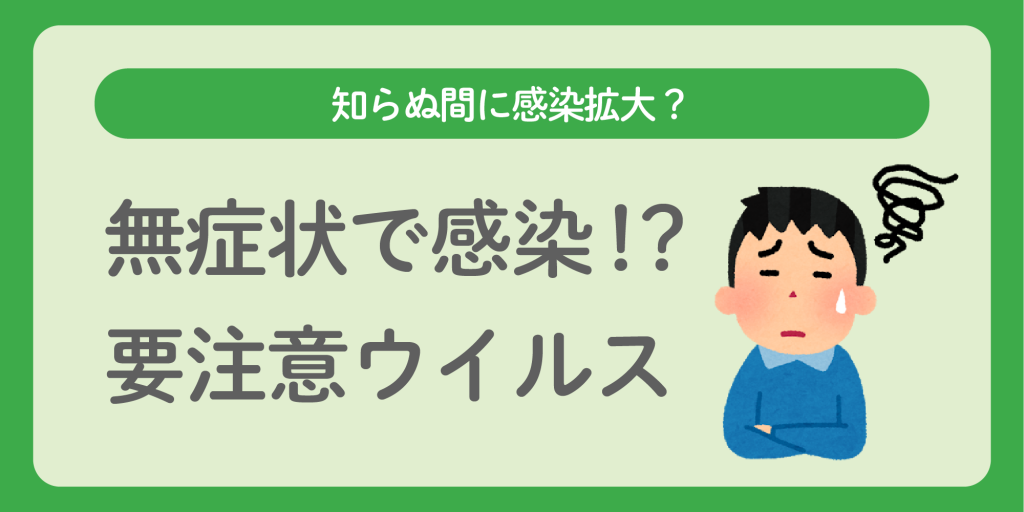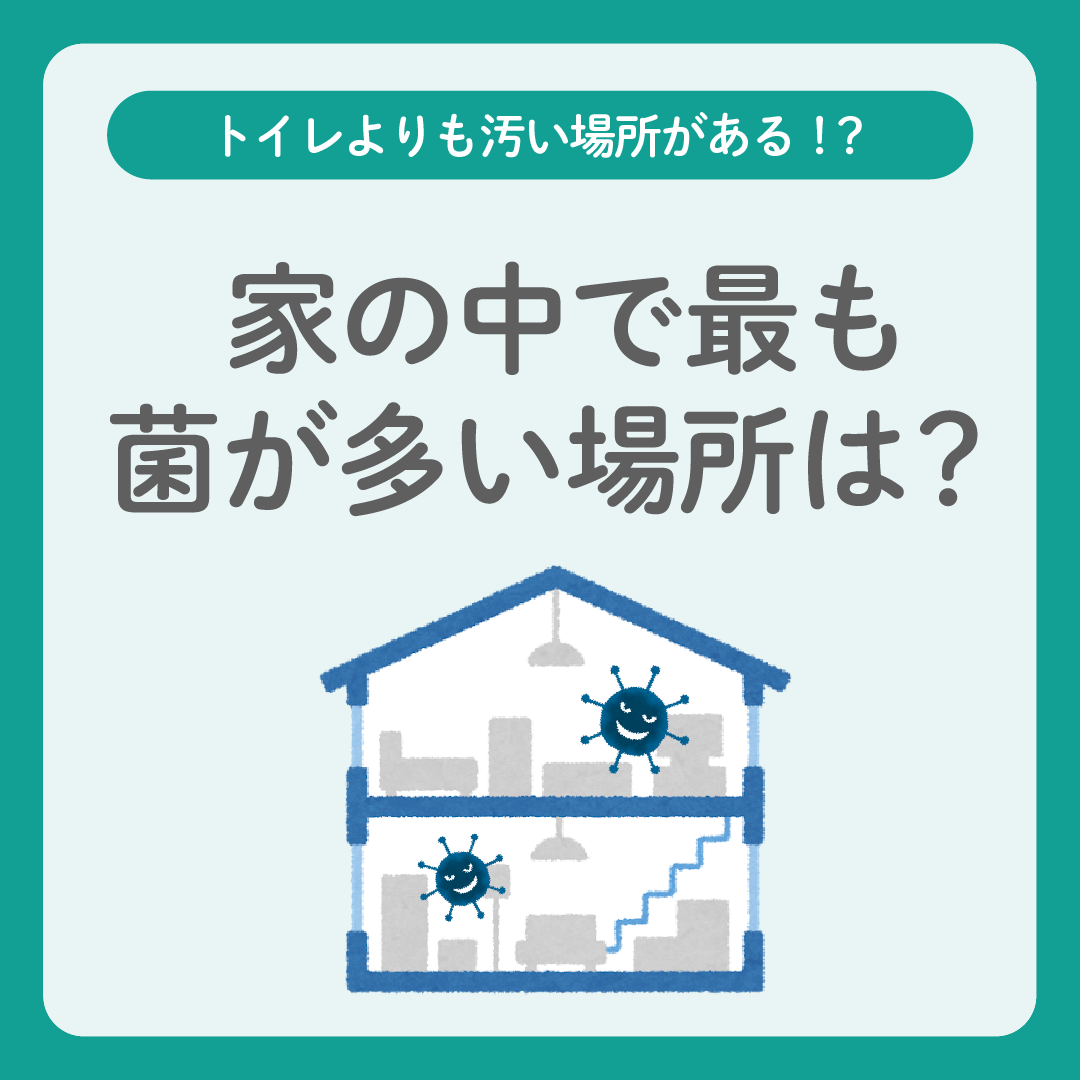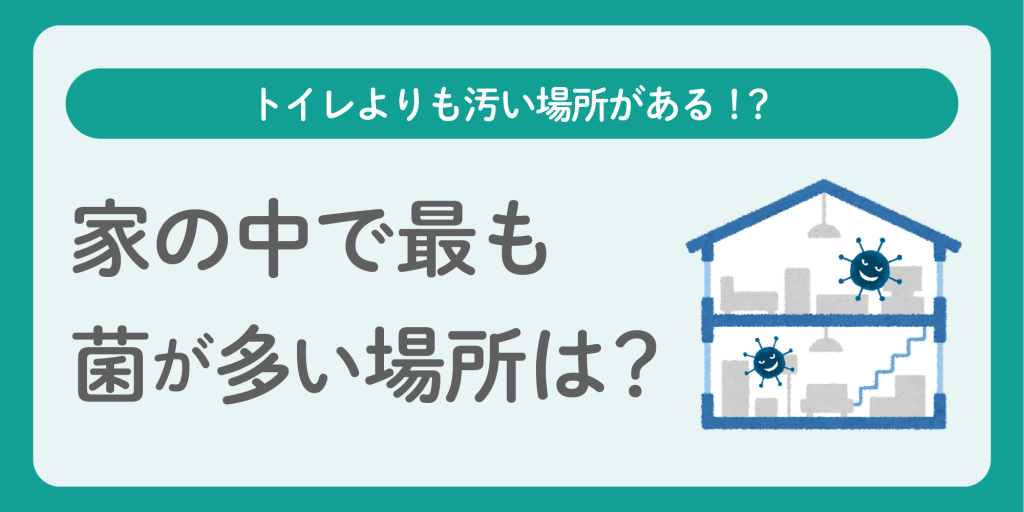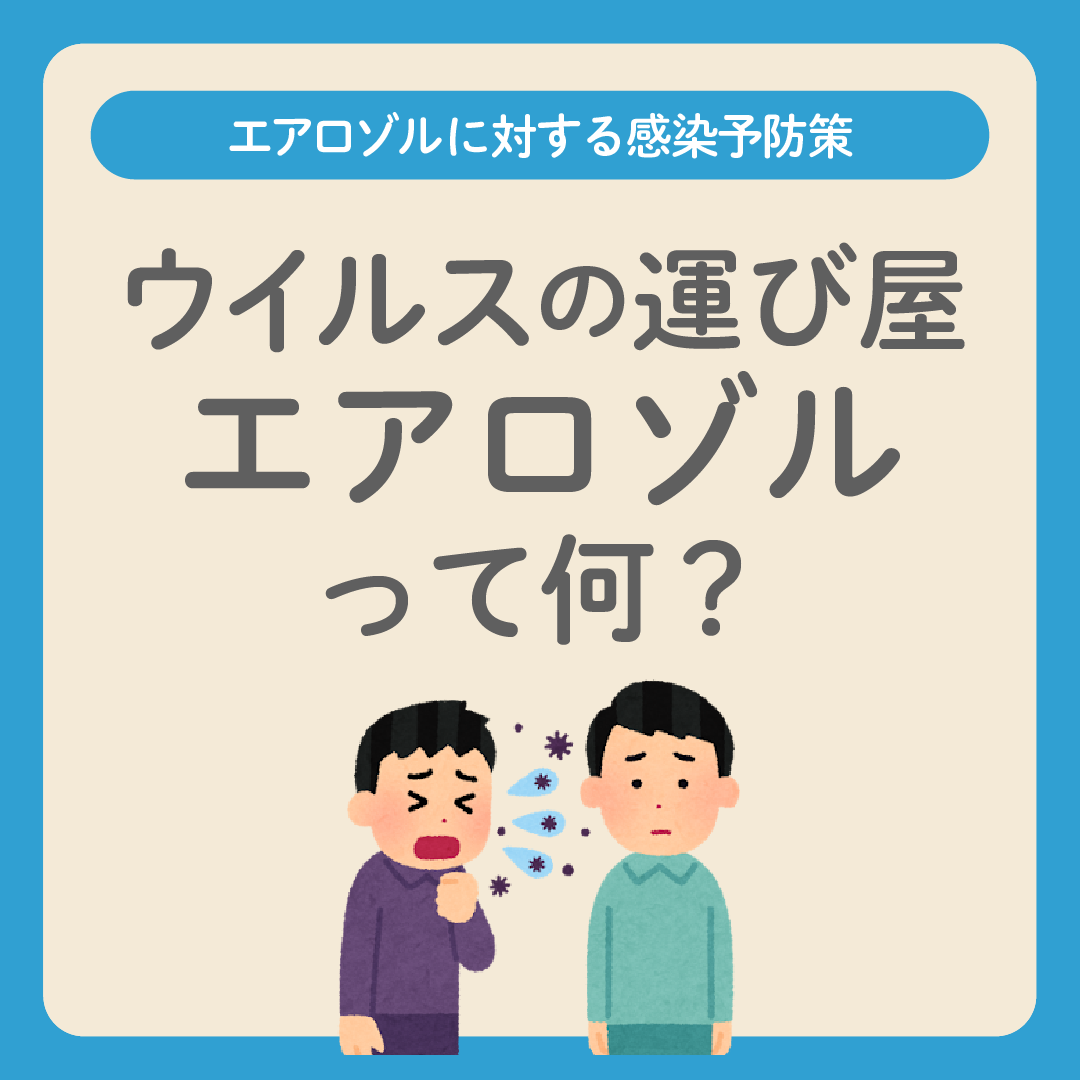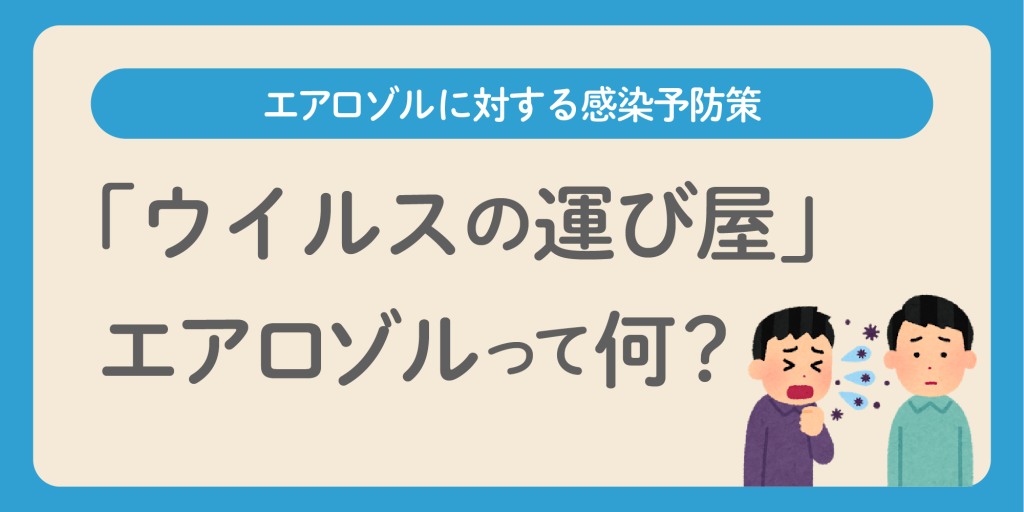清潔・快適に使うためのトイレマナー
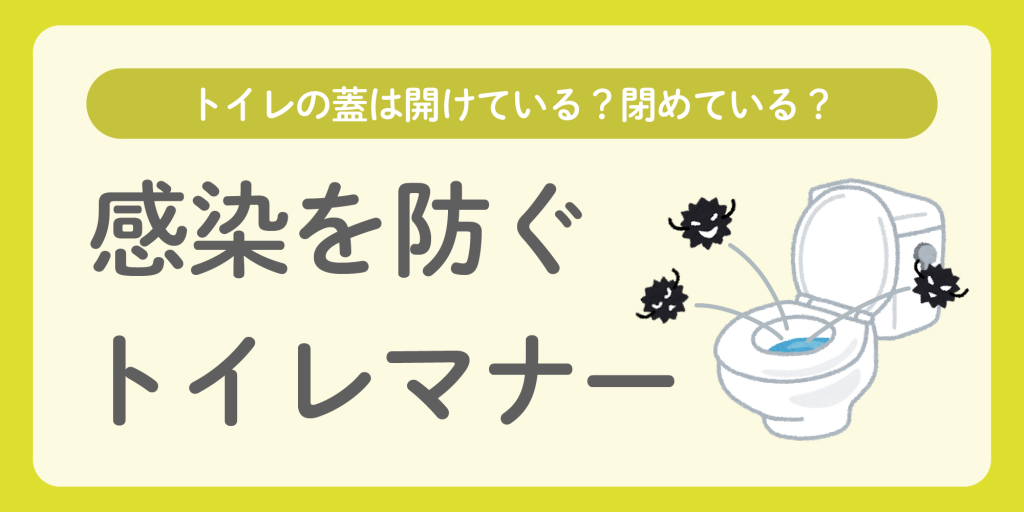
こんにちは、デンネツ広報担当です。
皆さんは飲食店などでトイレを利用した際、「トイレのフタを閉めてください」という貼り紙を見かけたことはありませんか?
実は、フタを閉めることにはさまざまな理由があるのです。
今回は、衛生面の豆知識とともに、フタを閉めることのメリットをご紹介します。
■トイレのフタを閉めることで得られるメリット
トイレを流す際にフタを閉めるのは、飛沫の飛散を防ぐためとよく言われますが、近年の研究では「フタを閉めても開けていても飛散量に大きな差はない」という説も出てきています。
それでも、フタには以下のような役割があります。
・便器内の水(封水)への異物落下を防ぐ
・便器の見た目を美しく整える
・断熱効果を高める(特に温水洗浄便座・暖房便座の場合)
※温水洗浄便座や暖房便座は電気で便座を温めています。
フタを閉めることで熱の放散を防ぎ、節電にもつながります。
たった一つの習慣、「便座のフタを閉めて流す」だけで、トイレ空間をより清潔で快適に保つことができます。
衛生的で見た目もスマート、さらにエコにもつながるこの習慣。
ぜひ、今日から意識してみてください!